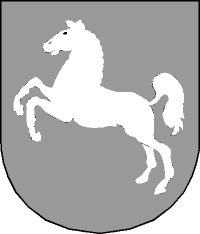近代化学の夜明け
| 近代化学の夜明け | |
|
<ボイルの元素論>
1661年にアイルランドの科学者ロバート・ボイル(1627~1691)が「懐疑的化学者」という著作を書き、その中で錬金術師(alchemist)を化学者(chemist)と呼びました。これ以後、化学は中世の魔術のイメージを払拭していくことになります。
ボイルは「元素はそれ以上分解できない究極の物質単位であり、どうしても分解できないことを証明して初めて元素と言える」と考えました。これ自体はあまりいい原則とは言えませんが、たとえばギリシャ時代の「地水火風が4大元素である」といった感覚的な元素論を打ち砕いた点では、科学時代の確かな幕開けを告げるものでした。
元素を「それ以上分解できないもの」とすると、また元素は2つ以上のものから作れないもの、つまり合成できないものということになります。1000年以上に及ぶ錬金術師たちの努力にもかかわらず金が作れなかったのは、金が元素だったからです。もし合成物だったら、いつかの時点で金を2つ以上の構成元素に分解できていたでしょう。ボイルは、この定義によって錬金術が空しい試みであったことを明確にしたのです。
しかし、この定義は不十分なものでした。なぜなら、「それ以上分解できない」というだけでは、ある物質が元素であるという証明は大変困難になるのです。「一生懸命分解を試みたけれども分解しなかった」というのは、「分解できない」という証明ではありません。「私には分解できなかった」という個人的な経験談に過ぎないからです。ほかにうまい方法があって、実は分解できるのかもしれません。
ボイルの時代は、ガス分析が非常に盛んでした。空気とは何か、蒸気とは何かということが熱心に研究されました。しかし、そうした中で炭酸ガスはなかなか分解できなかったので、初めのうちは元素だと思われていました。ずっと後になって、燃焼が酸化現象であるという考え方が生まれてくると、炭素が燃えて炭酸ガスができると分かって、実は炭酸ガスは元素でなく化合物だと判明したのです(現在では、炭酸ガスを分解する方法もあります)。
この頃までにはいろいろな植物の色素が酸やアルカリで色を変えることが知られていました。中でも有名なのはリトマスゴケという苔の一種が持つ色素成分で、現在のリトマス試験紙のもとになっています。料理するとき、酢を加えるなどすると、野菜の色が変化することはご存じですね。
アルカリとは植物を焼いた灰の成分(つまりカリウム)のことです。アルはアラビア語の定冠詞で、カリが植物の灰(主成分は炭酸カリウム)の意味です。英語ではポット(炉)の灰ということからポットアッシュ=ポタッシュ(potash)と呼ばれたので、カリウムのことをポタシウムと呼びます。
やがてニュートン(1642~1727)が登場すると、世界の事象はすべて要素の量的関係として数理的に解けるという近代計量科学の基礎が築かれることになりました。これは「虹は神の祝福なのか」「なぜ虹はあんなに美しいのか」と問う人に「太陽光はさまざまな波長の光が集まったもので、大気中を漂う水滴によってスペクトルに分割されるのでこう見える」と説くもので、感動や信仰に基づく「説明」と科学的な「解明」との間に違いがありました。一般の人々にはなんだか的外れな説明のように思われていましたが、計量的なアプローチは予測やそれに基づく行動、結果の検証といった具体的なアクションを引き起こすことが可能です。それが科学の客観性ということです。
1669年にヒトの尿からP(リン)が発見されました。中世以後久々の新元素発見です。発見したブラント(?~1692頃)は錬金術の金を作り出す物質がヒトの尿中にあるに違いないと思いこみ、自分の尿を煮詰めてみました。すると、その蒸発残留物の入ったフラスコが、暗い部屋の中でぼんやりと光ったのです。これがリンでした。ちなみにリンが光を出すのは、わずかずつ自然燃焼するためです。
<定量化学の基礎>
この時代の最大の化学者はラボアジェ(1743~1794)です。
それ以前にも多くの科学者は質量の不変やエネルギーの不滅を信じていましたが、燃焼によって重量が増えるものと減少するものがあることを説明できず、当時だれもが信じていた「フロギストン」説に基づいてかなりちぐはぐな説明をしていました。
フロギストン(燃素)とは可燃物の中にあると想定された一種の元素で、燃焼とはそれが抜ける現象であるという説が有力でした。木が燃えると質量を失って軽い灰が残りますが、このとき失われた質量がフロギストンの重さに相当するわけです。ところがこれでは、金属のように、燃えると重さが増すもののことは説明できません。
しかしイギリスの偉大な変人科学者キャベンディッシュ(1731~1810)が水素を発見し、ついでプリーストリ(1733~1804)が酸素を発見すると、いわばおぜん立てが整い、ついにラボアジェが「燃焼はフロギストンが抜け出る過程でなく可燃物の酸化反応である」と見抜きました。
ラボアジェは特に独創的な実験をしておらず、むしろ他人の行った実験結果を総合して一つの統一理論を打ち立てるタイプの理論科学者でした。
彼は物質(質量)が原因なく生成したり消滅したりするはずはないと信じていて、「何もないところから何かが生ずるとか、何かがあるのに、それがなくなってしまうと信ずるのは、バカだけである」と言っています。これは運動量保存の法則などと同様の考え方でした。
残念ながらラボアジェは敵が多く、ブルボン王朝の徴税請負人だったので、人民の憎しみを買っており、フランス革命でギロチンの露と消えました。
なおラボアジェが登場して、すぐにフロギストン説が消滅したわけではありません。フロギストン時代の化学者が高齢になって隠退し、あるいは死亡していなくなった後に、新しい化学の時代になったのです。化学だけでなく、サイエンスの世界では、古い説に固執する権威者がいなくなるまでは、その説に反する新しい考え方が主流になることはないようです。 |
|
| |
| もくじ |
|
|
 2.錬金術の時代  3.近代化学の夜明け  4.原子説と分子説  5.分光分析  6、周期表 7.質量分析と素粒子物理学 8.有機化学 9.クロマトグラフィー 10.希土類元素 |
|
| |