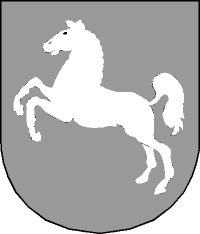原子説と分子説
| 原子説と分子説 | ||||||||||||||||||||||||||||
ラボアジェ以後、定量的化学の概念に基づく近代化学が発展し、化合物と元素の量的関係についての知見が広がってきました。当時多くの化学者は酸-アルカリ反応に大きな興味を持ち、これをもとに各化合物の間の当量関係を見出そうとしていました。
主要な元素のほとんどが見いだされたのもこの時期(18世紀~19世紀前半)です。先にふれた水素、酸素に次いで窒素、塩素、さらには長らく正体不明だったナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムといったアルカリ金属も発見されました(後述)。
キャベンディッシュは水素を発見したとき、水が元素でなく水素と酸素の化合物であることに気付き、空気中の酸素の濃度が約21%だということも突き止めていました。炭素が燃えると二酸化炭素になることは、もう少し早く分っていましたが、それが炭素と酸素だということは、プリーストリが酸素を発見するまではっきりしませんでした。
ドルトン(1766~1844)は1803年に「化学の新体系」を書いてさまざまな原子の重量に簡単な整数比の関係が成り立つと論じました。知られている最も軽い元素である水素の質量数を1とすると、どの元素も整数の質量数を持つというのでした。これは塩素がほぼ35.5という中途半端な質量数になることを考えるとかなり大胆な仮説でしたが、約100年後に質量分析器が登場するまで解決しませんでした。
ドルトンの原子説は、ほとんどの化学者に支持され、その後の化学に大きな影響を及ぼしました。しかし彼は水の分子はHOという1対1の量関係にあると考え、しかも彼が実験に用いた空気には不純物が混じっていることを知らなかったので、酸素の原子量は7であるとするなど、後からみるといろいろな間違いがありました。
1811年にイタリアのアヴォガドロ(1776~1856)が分子説を発表しました。一定の圧力と温度のもとでは、等しい体積中の気体粒子の数は気体の種類にかかわらず一定であるという仮定に基づき、水素や酸素はそれぞれH2、O2という2原子分子になっているという説です。たとえば水は水素2対酸素1から成り、できた水(水蒸気)は容積1になります。
残念ながらこの説は約半世紀の間無視され、化学者たちは長い間混乱した実験結果を受け入れていました。1860年にケクレ(1829~1896)が開催した国際会議で、イタリアの化学者カニッツァーロ(1826~1910)がアヴォガドロ説を使うといろいろな矛盾が解決することを力説し、やっと公認されるようになったのです。
水素ガス2gの占める体積(常温で約24リットル)中にはアヴォガドロ数個の水素分子があり、どんな気体でもその体積中に同じ個数の分子があります。同体積=同個数という考えそのものは古くからあったのですが、構成単位を原子でなく分子として考えることで複雑だったパズルをすっきりと解くことができたのです。
ベルセリウス(1779~1848)はアヴォガドロ説が受け入れられていなかった時期の大化学者です。希土類元素をいくつか発見しただけでなく、精力的に多数の実験を行い、多くの化合物の組成を突き止めて、当時知られていた元素の原子量を決定しました。
ベルセリウスの原子量表の一部
(カッコの中の数値は2H=2とした場合)
(サバドバリー「分析化学の歴史」(内田老鶴圃:1988より)
多くの元素が現在の半分の値になっているので面喰ってしまうのですが、よく見ると水素だけは2Hで、その原子量が1と記載されています。仮に水素を0.5とすると、一部の元素(ナトリウム、カリウム、銀など1価の金属)は今の値とほぼ同じ数字が書かれているので、ちょうど2倍ということになります。2価の元素である酸素、水銀や、陰イオンとして水素と1対1で結びつくフッ素、塩素などは、2分の1の原子量になっています。当時も「この値の2倍だ」「いや、この半分にすれば合う」と論争の的になったようです。
アヴォガドロの分子説を知らないばかりに、こんなに混乱していたのですね。
しかし彼の実験は周到で巧妙なものだったことが残された著書からもうかがえ、現在でも参考になるものがあります。実験器具も工夫されていて、図を見る限りでは今用いているものとほとんど違いがありません。
ベルセリウスはまた、化合物を有機化合物と無機化合物に大別した人でもあります。無機物は、普通の化学反応の多くが可逆的です。たとえば酸化物は還元して金属と酸素に分解したり、もう一度化合させて酸化物にすることができます。ところがタンパク質などは、加熱すれば変性して、冷やしても元に戻りません。分解すると炭酸ガスや水などになり、これを元のタンパク質に戻すことはできません。そこで有機物は生命体によってのみ作り出されるもので、実験化学的に造ることはできないと考えました。
この頃は電磁気学が発展しました。水を電気分解すると水素と酸素が容積比で2対1の割合で発生することが知られていました。重量比で1対8であることも分かっていました。ベルセリウスは無機物の分析を行っていましたので、物質には二種類の電気を帯びたものがあり、それが互いに反応すると思っていました。これは無機イオンの反応に関する限り、正しい仮説でした。
イギリスのデーヴィ(1778~1829)は1807年に植物を燃やした後の灰は何からできているのだろうと疑問を持ち、電気分解することを試みました。最初は灰を水に溶かして電気を通じてみましたが、発生したのは水素と酸素でした。溶かすのに使った水が分解されただけだったのです。
ところが、灰に電極を差し込んでも電流は流れません。どう考えたかは分かりませんが、解決法は独創的でした。彼は灰を白金製の容器に入れ、加熱して溶融させ、それに白金製の電極を差し込んで分解したのです。このために大きな電池を自作したということです。植物の灰の主成分は炭酸カリウムでしたので、これによって金属カリウムが分離されました。この他、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウムなどの元素を次々に発見しました。一人で発見した元素数としては、デーヴィが最多記録とされています。
彼の弟子だったファラデー(1791~1867)は1832年に電気分解に関する法則を発表しています。彼は電解液中に「イオン」が存在すると考え、陽極(アノード)に向かって移動するイオンをアニオン(陰イオン)、陰極(カソード)に向かって進むイオンをカチオン(陽イオン)と呼びました。この用語は今も使用されています。
[電解質]
水に何らかの物質(溶質)を溶かすと、溶質の濃度に応じて氷点が下がります。モル凝固点降下という現象で、モル濃度(分子量が60なら1リットル中60グラムを1モル溶液という)によって決まるので、分子量が分らない物質でも溶かして氷点の低下の程度を調べればモル濃度が分り、それから分子量を割り出すことができます。沸点上昇という現象もあり、やはり溶質のモル濃度に比例します。
この他、浸透圧の大きさもモル濃度に依存します。より精密に分子量を調べるには、浸透圧の測定が用いられます。ところが、これらの実験は、ショ糖などの溶液では、よい結果が得られるのですが、食塩(NaCl)などで実験すると、理論値の2倍近い値が得られます。その理由は長い間不明でした。
ファラデーの半世紀のちの1884年、スェーデンの大学の化学科の学生だったアレニウス(1859~1927)は「もしかしたらNaClはNaとClに分かれて溶けているんじゃないでしょうか」と言い出して、教授からこっぴどく叱られました。「原子状に分かれて溶けているだと?バカも休み休み言え。水に溶かしただけで分子が形を変えるわけはないぞ」と言われたのです。
また「それならNaのように軽い原子は上に浮かび、Clは重いから下に沈むことになるはずだ」とも批判されました。
しかしアレニウスはこの問題を考え続け、ついにNaはNa+、ClはCl-という荷電粒子(イオン)に分かれているという結論に達し、博士論文にその考えを書いて提出しました。これならNaとClは電気的に引き合っているので、ばらばらになってNaだけが上に浮かんだりはしません。論文は散々な不評で、落第すれすれの最低点でやっと合格しました。教授たちには、究極の不変の粒子である原子が、水に溶かしただけでイオンなどというものに姿を変えるはずはないとしか思えなかったのです。
その後もアレニウスは実験を続けて証拠を積み重ねました。「電解質」が溶けている水の電気伝導度が大きくなることはイオン電流の考え方で説明できます。他の化学者からもアレニウスの説を支持する声が次第に高くなり、その後電子が発見されると、ついには彼の博士論文に対してノーベル賞が贈られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
| もくじ |
|
|
 2.錬金術の時代  3.近代化学の夜明け  4.原子説と分子説  5.分光分析  6、周期表 7.質量分析と素粒子物理学 8.有機化学 9.クロマトグラフィー 10.希土類元素 |
|
| |